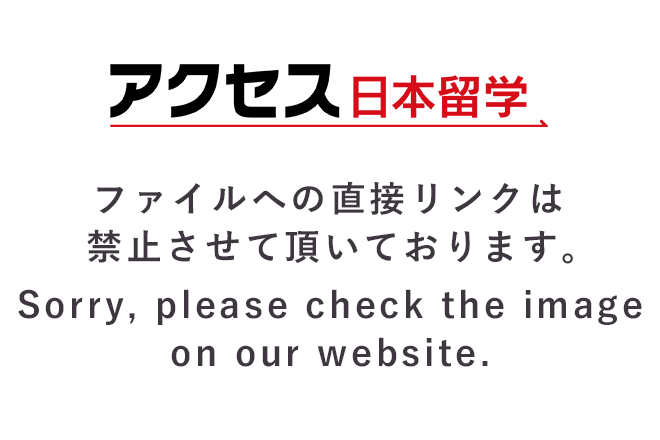
UPDATE | 2022年06月27日
この記事では、外国人が日本の病院で診察を受ける流れを詳しく解説します。また、外国人が病院で困ること(医者に言葉が通じない、どの病院に行けばいいのか分からない、健康保険や医療費の金銭的な不安など)についての解決策もお伝えしていきます。
INDEX
医療制度は国によって異なりますので、まずは日本の医療の仕組みについて簡単に説明します。
日本では、全員公的医療保険に入ることになっています。そして、病気やケガをしたときには、基本的に予約なしで、どの病院や診療所でも診療してもらうことができます。
かかった治療費は原則3割を本人が負担しますが(公的保険が残りの7割をカバー)、保険適用外の治療を受けた場合は全額負担となります。
日本の医療制度については、あとでさらに詳しく解説します。
[PR]
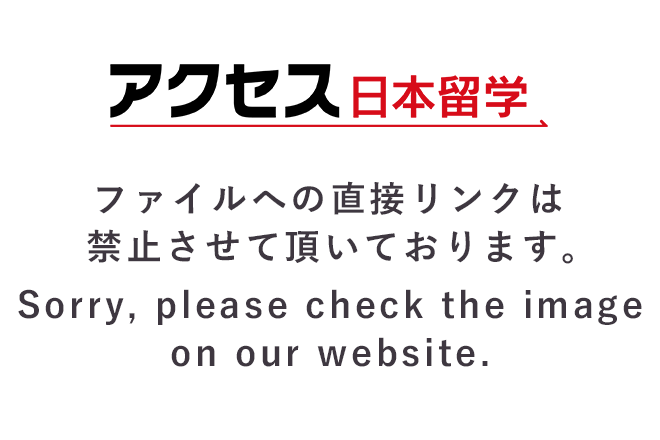
喉の痛みや発熱がある場合は、まず新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口に連絡してください。都道府県ごとに窓口が異なりますので、お住まいの地域の情報を確認しましょう。各都道府県が公表している、相談・医療に関する情報や受診・相談センターの連絡先は以下で確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
外国人が日本で診察を受けるときの一般的な流れは次のようになっています。
1.診療申込書に記入する
2.保険の加入状況を知らせる
3.身分証明書を見せる
4.支払いに関する事前説明を受ける
5.どれくらい医療費がかかるか、おおよその額を聞いてみる
6.問診票に記入する
7.診察を受ける
8.診断書が必要な場合は発行をお願いする
9.医療費を支払い、処方箋を受け取る
それでは、それぞれのステップについて詳しく解説していきます。
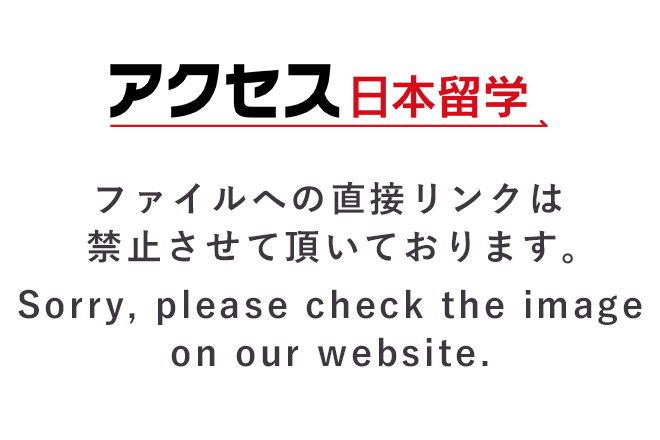
「医療に関するやりとりは、普段の会話より難しいです。日本語に不安のある方は、行こうと思っている病院や診療所に
・外国人も診てもらえるか?
・日本語以外で対応可能な医師やスタッフがいるか?
を事前に問い合わせるとよいでしょう。もし日本語ができる友人が身近にいたら、病院への問い合わせを手伝ってもらったり、診療に付き添ってもらってもよいと思います。
診療をスムーズに進めるため、病院や診療所では診療申込書を用意しており、その記入を求められます。
氏名、住所、性別、年齢、連絡先(電話番号)といった個人情報とともに、
・この病院で診療を受けるのははじめてか
・紹介状はあるか
・診療の予約をしているか
・医療保険の加入状況
・気になる体の状態(診療を希望する理由)
・母国語、母国語以外に話せる言語
・通訳を必要としているか
・宗教上の理由で特に配慮してほしいこと
など、診療に関することに答える必要があります。
ここで記入した情報をもとに診療を進めますので、正直に答えてください。
日本の公的医療保険に入っているかどうかを病院に知らせましょう。入っていれば治療費の3割を負担、もし入っていない場合は全額負担となります。日本の公的保険に入っていても保険証を忘れてしまった場合は、全額支払いとなり、後日、保険証を見せることで差額を返してもらうことになります。
自国の公的医療保険や海外の民間保険は入っていても、全額負担になるので注意してください。もし民間保険の対象となるケースでも、日本でかかった治療費は一度、全額を支払ったうえで、後日、保険会社に請求する必要があります。
パスポートか在留カード(日本に3か月以上滞在している外国人のみ所有)を提示します。
日本と海外では、外来・入院の流れや診療方法が異なる場合があります。医療費の支払いは、その代表的な例として挙げられますので、日本での診療から医療費の支払いまでの流れをよく確認をしましょう。
治療にどのくらいの費用がかかるのか、おおよその額を参考までに聞いてみましょう。診断や治療によって費用は異なりますが、金銭面での不安を取り除くことができるかもしれません。
日本では、医師の考え・方針にのっとって検査や治療を進め、最後に提示された医療費を支払うのが一般的ですが、「医療も契約の一部。納得するまですり合わせる」というのが前提の国の方だと抵抗を覚えることもあるでしょう。
治療前にどんな治療をするのか、どれくらい費用がかかるのか、教えてもらってから治療を受けるかどうか決めたいという場合は、そうした希望があることも伝えましょう。
問診票は、あなたの病状についての詳しい情報を医師に伝え、より的確に診断を行う上で重要なものです。特に日本語がまだ不慣れな方は、対話で症状を伝えることが難しいので、問診票を活用し正確に症状を伝えましょう。
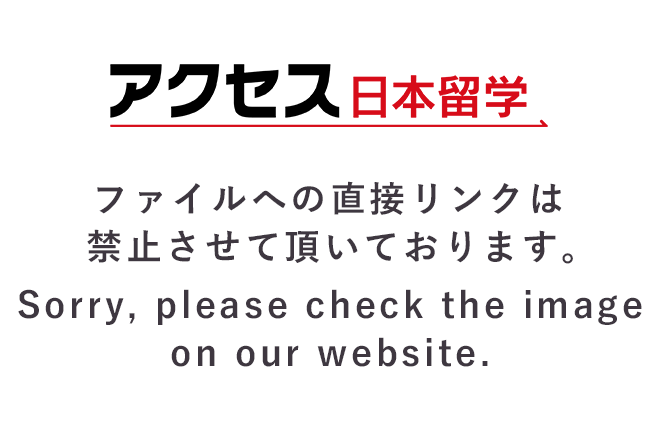
具体的な症状など、問診票では伝えきれない部分を話しましょう。伝えた内容をもとに医師が必要な検査や処置をします。
後日、保険会社への請求などで診断書が必要な場合は、発行を依頼する必要があります。診断書を発行するためにいくらかかるか、支払い方法、受け取りはどうすればいいか、対応可能な言語は何か(日本語の診断書しか出していないところもあります)などについて確認してから依頼しましょう。
診察が終わると、今日はどのような治療を行ったのか書いた紙を渡されるので、会計窓口に提出します。それをもとに計算した医療費が提示されますので、決められた方法で支払いしてください。お金の支払いはトラブルになりがちです。支払いが完了したことを証明するものとして領収書は忘れずにもらってください。
薬が処方されている場合は処方箋が出されます。ここまでで病院での診療は終わりです。
処方箋は薬局に持っていき、薬をもらいましょう。日本全国どこの薬局でも大丈夫ですが、病院で払った診察代とは別に薬代がかかります。
日本で病院にかかる場合は、
・病院に行き、自分の名前や住所、年齢などの基本情報と診てもらいたい身体の症状を伝える
・身分証や保険証を提出し、間違いがないか確認
・医者の診察を受ける
・受けた検査や治療の内容をもとに費用が請求されるので、支払う
・薬が処方されている場合は、処方箋を受け取り、薬局で薬をもらう
というのが基本の流れになります。
日本では診察内容や請求額をあらかじめ示してもらい、納得したら治療を受ける、という慣習がないので、外国人が治療を受けたとき、費用の支払いをめぐってトラブルになることがあります。
日本の医療事情を踏まえたうえで、「こうしてほしい」という要望があれば、積極的に伝えたり、都度確認するなどしていきましょう。
また、病院に行くのに必要なものを下記にまとめました。病院に行く準備をするときに参考にしてください。
【日本の病院で必要となる持ち物】
・健康保険証(日本の公的医療保険に加入している方)
・身分証明書(パスポートまたは在留カード)
・現金またはクレジットカード。(クレジットカード払いができない病院も多いので、現金を持っていくことをおすすめします)
ここからは外国人が日本の病院で困ることについてお伝えします。
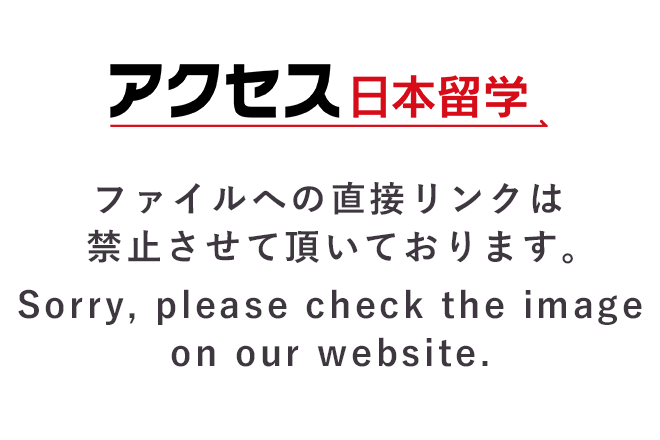
外国人が日本の病院で診察・治療を受けるとき、どのようなことに一番困っているのでしょうか。
出入国在留管理庁による「令和2年度 在留外国人に対する基礎調査報告書」によると、外国人が日本の病院で困ることは「病院で症状を正確に伝えられなかった」「病院の受付でうまく話せなかった」と「言葉が通じない」ことが一番多く、それ以外にも「病院の選び方」や「医療費」などがあがっています。
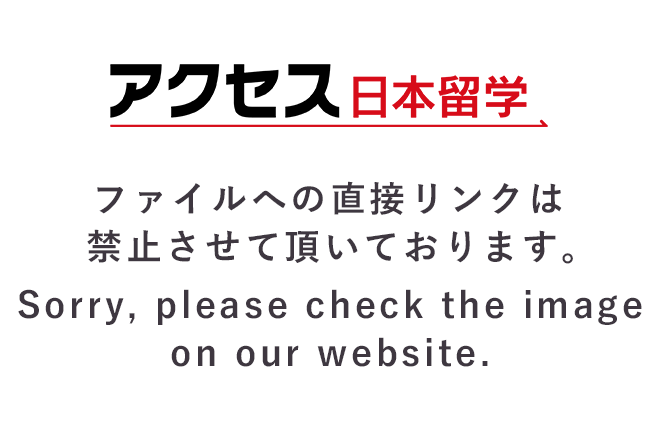
出典:出入国在留管理庁「令和2年度 在留外国人に対する基礎調査報告書」
また、日本で暮らす外国人向けて、暮らしに関するさまざまなサービスを提供する会員制メディア「株式会社YOLO JAPAN」が行なった別の調査でも、やはり1位「日本語が話せない/外国語対応できる人がいない」と「言葉が通じないこと」、2位は「何科に行けばいいか分からない」と共通しています。
病院で困ったことは何か?
1.日本語が話せない/外国語対応できる人がいない 50%
2.何科に行けばいいか分からない 29%
3.待ち時間が長い 26%
4.治療費、保険料が高い 23%
出典:株式会社YOLO JAPAN「日本の医療サポートに関する調査」
日本に住む外国人が日本の医療機関を利用する際、一番困ることは、受付や医師と話す際に言葉が通じないことや、自分の症状が説明できないことなど、言葉の壁であることがわかります。
そこで、病院の受付でのやりとりや医師に自分の症状を伝えるときに役立つ情報を二つ、紹介します。
質問に答えると自動翻訳して日本語で問診票を作ることができるサービスで、英語、ベトナム語、ポルトガル語など、17言語に対応しています。病院に行くときに作って持っていくことで、自分の症状を正確に伝える助けになります。
日本を安心して旅していただくために 具合が悪くなったときに役立つガイド
日本政府観光局が提供している日本で医療を受けるときに役立つウェブサイト。病院の検索ができ、地域、対応言語、医療科目、利用可能なクレジットカード、拠点的な医療機関(都道府県に選ばれた外国人患者の診療の拠点となる病院)、JMIP(多言語による診療案内や、異文化・宗教に配慮した対応をしてくれるか)、救急対応してくれるかなどがわかります。
「言葉の壁」の次に外国人が日本の病院で困ることとして、体調の異変や何らかの症状が出ていても「どの診療科を受診すべきか分からない」という不安があります。その場合の解決策をお伝えします。
頭痛、腹痛、風邪などのよくある症状は、内科を受診してください。それ以外の症状の場合について、以下で解決策を考えていきます。
気になる症状と「何科を受診」というキーワードでネット検索すると、さまざまな情報が出てくると思いますが、信頼できるもの/できないものが混在しています。誰が発信している情報なのかを調べ、医療機関や医師が提供している信頼度の高いものを参考にするとよいでしょう。
また、たくさんの診療科がある総合病院・明和病院が、よくある症状と何科を受診すればよいかをまとめたものを公式サイトで公開しています。
受診するときの参考になると思います。
急なケガや病気などで、「すぐ病院に行ったほうかいいか?」「救急車を呼んだほうかいいか?」と迷う場合は「#7199」(緊急安心センター事業)に電話してください。
医師や看護師、トレーニングを受けた相談員が状態を聞きとり、緊急性が高いかどうかを判断し、必要であれば救急車の手配をしてくれます。緊急のケースではないと判断された場合も、どの医療機関を受診できるか案内してもらえます。
この事業を別の番号で実施していたり、実施していないエリアがあったりするので、「もしも」の場合に備えて、ご自身がお住まいの地域の状況を確認しておくとよいでしょう。
緊急でない場合は、たくさんの診療科が入っている総合病院に電話で相談することをおすすめします。大きな病院は診察してもらうのに予約や紹介状が必要なことも多いので、事前に問い合わせしておいたほうがよいからです。
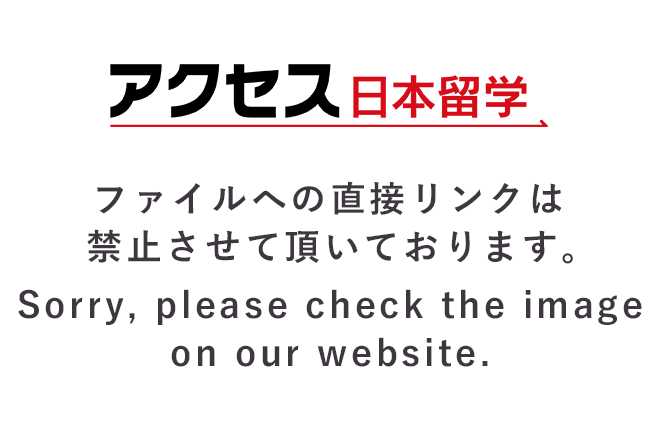
外国人が日本の病院で困ることとして、金銭面(健康保険・医療費)もあります。
冒頭でも説明しましたが、日本の公的医療保険に加入していないと、医療費は全額負担となります。日本の公的医療保険に加入している場合、保険証を提示すれば、個人が払う医療費は3割負担になります。(残りの7割は公的保険でカバー)
自国の公的医療保険、海外の民間保険の場合は、加入していたとしても、先ほど(「外国人が日本の病院で診察を受ける流れ」の「2.保険の加入状況の確認」)お伝えしたとおり、日本では適応されませんので医療費は全額自己負担となります。
日本では公的医療保険は健康保険法に基づいて運営されているので、「健康保険」と呼びます。観光などを目的に日本に滞在する人を除いて、日本では安心して医療を受けられるように、すべての人が健康保険に加入することになっています。
健康保険には大きくわけて3つ、主に会社勤めの人が加入する「被用者保険(職域保険)」、自営業や退職した人が加入する「国民健康保険」、75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療保険」があります。
健康保険料は加入している保険や所得により変わってきますが、所得が大きくなるほど負担額も大きくなります。
国民健康保険は都道府県と市区町村が運営しています。日本に3か月以上滞在する外国人で、会社の健康保険に入っていない人は国民健康保険に入る必要があります。また、入国したときには滞在が3か月未満の予定でも、その後、3か月以上滞在することになった場合は国民健康保険に入らないといけません。滞在期間が3か月を超えている人は注意してください。
健康保険(社会保険と呼ばれることもある)は会社に勤める人が加入する保険です。国籍を問わず加入する義務がありますので、外国籍の方も加入しなければなりません。
冒頭でお伝えした通り、外国人でも健康保険に入っていて保険証を提示すれば、個人が払う医療費の負担は日本人と同じ3割(30%)です。
また、留学生の場合の保険料は、前年中の所得(アルバイト等)に基づいて計算されます。所得が申告されていないと正しい保険料の計算ができないので、お住まいの市区町村の役場で必ず申告してください。前年の所得が一定基準以下の場合、保険料が減額されます。所得がなかったり、少なかった場合でも、所得の申告が必要なので、忘れずに申告しましょう。
外国人が日本の病院で困ることの最後に、病院の待ち時間を考えてみます。
「病院では長く待たされる」とよく言われますが、厚生労働省が公表している資料(令和2(2020)年受療行動調査(概数)の概況)によれば、外来患者の診察等までの待ち時間は「15 分未満 」が27.9%と最も多く、次いで「15 分~30分未満 」が25.8%、「30 分~1時間未満」が20.9%となっており、約7割が1時間未満の待ち時間で診察を受けています。
厚生労働省のこの調査では待ち時間はあまりないという結果になっていますが、病院によっては待ち時間が長いところがあるのも事実。ここからは病院の待ち時間が長くなってしまう理由と、解決策として予約について解説します。
病院での待ち時間が長くなってしまうのには、いくつか理由があります。
まず、多くの人が病院に行きたいと思う時間が重なるということ。たくさんの人が同じ時間に集中して集まることで待つ列ができ、どんなに効率よく診療を進めたとしても、そこに後から人が次々やってくると列は長くなってしまいます。
次に、患者さんの状況を把握するのに時間がかかることがあるという点があげられます。適切な診察、治療のためには、患者さんの現在の状態をきちんと把握することが必要です。しかし、そのためにはある程度、コミュニケーションに時間をかけなければなりません。初めて診る患者さんの場合はとくに、その点で時間がかかってしまうことがあります。
最後に、診療報酬の計算はとても複雑です。計算して請求額を出すまでに時間がかかると、会計で待たせてしまう状況が発生します。
これら一つひとつは小さなことでも、重なっていくことで「患者が長く待たされる」という状態になってしまうのです。
病院内での混雑や待ち時間のストレスを減らすため、病院によっては診療予約ができるところがあります。予約の仕組みは病院によって違いますが、大きくわけて順番予約と時間予約の2種類があります。
・順番予約
その日の診察順を予約できます。たとえば「5番」だったらその日の5番目に診察してもらえる、ということです。順番に見てもらえるので公平性はありますが、遅い番号になるほど待ち時間が読めないのが困る点です。
・時間予約
「○日の○時に来てください」と来院時間を決めて予約をとります。病院に行く時間がはっきりわかるのがいいところですが、前の時間の人の診察に時間がかかってしまったなどの事情で待たされることもあります。
予約できる場合は事前に予約して、少しでも診療をスムーズに受けられるようにしましょう。診察時間が近づいたら事前に登録しておいたメールアドレスに知らせてくれるなど、それぞれの病院では少しでも待ち時間が少なくなるように工夫しています。
最後に、これまで見てきたことを簡単におさらいしていきましょう。
日本では、病気やケガをしたときには、基本的に予約なしで、どの病院や診療所でも診療してもらうことができます。
外国人でも健康保険に入っていて保険証を提示すれば、個人が払う医療費の負担は日本人と同じ3割(30%)です。
そして、日本では国籍に関係なくすべての人が健康保険に入ることが義務付けられており、外国人も例外に当てはまらない方は何らかの健康保険に入らなければなりません。
外国人が日本で診察を受けるときの一般的な流れは次のようになっています。
・病院に行き、自分の名前や住所、年齢などの基本情報と診てもらいたい身体の症状を伝える
・身分証や保険証を提出し、間違いがないか確認
・医者の診察を受ける
・受けた検査や治療の内容をもとに費用が請求されるので、支払う
・薬が処方されている場合は、処方箋を受け取り、薬局で薬をもらう
注意していただきたいのは、日本では診察内容や請求額をあらかじめ示してもらい、納得したら治療を受ける、という慣習がないので、外国人が治療を受けたとき、費用の支払いをめぐってトラブルになることがあるということです。少しでも疑問や不安に思うことがあれば、都度、確認していくようにしましょう。
外国籍の方が日本で病院にかかるときに困ることへの対処法です。
・言葉が通じない
医療に関するやりとりは日常会話より難しいです。日本語でのコミュニケーションに不安がある場合は、日本人や日本語が話せる友人・知人にサポートしてもらえるのが一番いいと思います。また、外国語での対応が可能な病院を探して受診するという方法もあります。
医療に関するやりとりは日常会話より難しいです。日本語でのコミュニケーションに不安がある場合は、日本人や日本語が話せる友人・知人にサポートしてもらえるのが一番いいと思います。また、外国語での対応が可能な病院を探して受診するという方法もあります。
ウェブ上で外国人が日本の病院にかかるとき、スムーズにやりとりするための情報やサービスが提供されていますので、ぜひ活用してください。
・何科に行けばいいのかわからない
ネットで信頼できる情報を探してみましょう。
また、緊急の場合(救急車を呼ぶかどうか迷うような状況)は電話相談にのってもらうこともできます。
・長く待たされる
病院によっては予約制度を取り入れているところがあります。予約制度を利用し、診察に必要となる情報、先生に聞きたいことをあらかじめまとめておくなど、スムーズに診察してもらえるよう、できることはやっていきましょう。

アクセス日本留学 編集部。外国人留学生のみなさんが日本の学校を見つけるための資料請求ができるWebサイト「アクセス日本留学」の運営や「外国人留学生のための進学説明会」を開催しています。
[PR]
[PR]